はじめに
「もしものときのために」と生命保険に入っている人は多いと思います。確かに、大切な家族のために備えるという考え方はとても立派なものです。でも、ふとこう思ったことはありませんか?
「保険に入るくらいなら、その会社の株を買った方がよくない?」
今回は、そんなちょっと視点を変えたお金の考え方を紹介します。
生命保険の控除額は意外と少ない
生命保険に入ることで、確定申告や年末調整で「生命保険料控除」が受けられます。これは節税になるメリットとしてよく紹介されますが、実際の金額はごくわずかです。
たとえば、年収500万円の会社員が新制度の「一般生命保険料控除(最大4万円)」をフル活用した場合の節税効果は以下の通りです。
| 税目 | 控除額 | 税率 | 節税額 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 4万円 | 10% | 4,000円 |
| 住民税 | 2.8万円 | 10% | 2,800円 |
| 合計 | – | – | 6,800円 |
つまり、年間12万円の保険料を払っても、戻ってくるのは約6,800円程度。
「節税のために入る保険」というのは、コスパが悪いというのが現実です。
保険の仕組みと、実際にかかるコスト
生命保険の多くは「掛け捨て型」です。つまり、一定期間なにもなければお金は戻ってきません。
また、貯蓄型の保険は途中解約で元本割れするリスクもあり、利回りも低め。総合的に見ると、
- 定期保険:掛け捨てでリターンはゼロ
- 養老保険・終身保険:リターンは低く、途中解約リスクも高い
となり、“備える”ためのお金が、効率的に働いているとは言えないことも多いのです。
そのお金で保険会社の株を買うという選択
ここで本題です。
毎月1万円の保険料を払う代わりに、そのお金で生命保険会社の株を買ってみるという選択肢を考えてみましょう。
たとえば、以下のような保険関連の銘柄があります:
- 第一生命ホールディングス(8750)
- T&Dホールディングス(8795)
- MS&ADホールディングス(8725)
これらの会社の株は、**配当利回りが3〜5%**と比較的高水準。つまり、「保険料を払う側」ではなく「株主として配当を受け取る側」になることができるのです。
保険会社の儲けは誰に分配されているのか?
保険は本来、相互扶助、つまり「困ったときはお互いさま」の精神で成り立っています。
ところが実際は、保険会社は上場しており、その利益は株主へ配当という形で分配されています。
これはつまり、私たちが払った保険料の一部が、投資家=お金持ちに配当という形で流れているということ。
「お金がないから保険に入る人」がお金を払い、
「お金があるから株を持っている人」が配当を受け取る。
こうした構図は、保険の「助け合い」という理念から少しズレてしまっている印象もあります。
だからこそ、「自分が株主になってその仕組みの“受益者”側に回る」というのは、一つの選択肢として非常に合理的です。
シミュレーション:毎月1万円の保険料を株に回したら?
仮に、毎月1万円を10年間、配当利回り4%の保険会社株に投資したとします。
- 累計投資額:120万円
- 毎年の配当金(単純計算):約4.8万円
- 10年後には年間で約5万円の配当収入が見込める
しかも、株価が上がれば含み益も得られる可能性があります。
これは、途中解約リスクがある保険よりも、資産としての柔軟性が高いというメリットもあります。
最後に:本当に備えるべきリスクにだけ保険を使う
もちろん、すべての保険を否定するつもりはありません。
- 小さなお子さんがいる家庭で、親に万が一があった場合 (掛け捨ての死亡保険など)
- 高額医療費が必要になるような突発的な病気
- 葬儀費用の備え
など、必要最低限の保障はあってもいいと思います。
ただ、あくまで「保険は安心を買うもの」「投資はリターンを求めるもの」と役割を分けて考えることで、より賢いお金の使い方ができるようになるのではないでしょうか。
まとめ
- 生命保険は、節税効果もリターンも限定的(年間最大6,800円ほどの節税)
- 保険料がそのまま“株主への利益”になっている構図を考えると疑問も
- 保険会社の株を買って、自分が“受け取る側”に回るという選択もあり
- 保険は最低限にして、投資と併用するのが賢い戦略






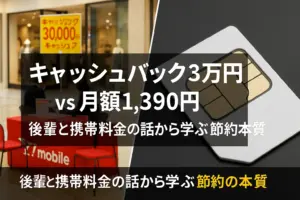

コメント