子どもの教育費をどう準備するかは、多くの家庭にとって悩みの種です。中でも学資保険は昔から定番の選択肢のひとつですが、「本当に今の時代に合っているのか?」と疑問に感じる方も多いかもしれません。
今回は、具体的な学資保険のシミュレーションを行い、投資と比較しながらそのメリット・デメリットを検証してみました。
学資保険というと、「利回りが低い」「元本割れのリスクがある」といったネガティブなイメージを持っている人も多いかもしれません。
しかし、実際に具体的なシミュレーションをしてみると、意外に悪くないという印象を受けました。
今回の学資保険シミュレーションの内容
- 保険種類:学資保険(無配当)Ⅲ型・22歳満期
- 被保険者:0歳 男児
- 契約者:30歳 男性
- 保険料:年払い164,548円 × 10年間(計1,645,480円)
- 保険料払込期間:10歳まで
- 学資金の受け取り:18歳〜22歳に毎年40万円ずつ(計200万円)
- 返戻率:約121.5%
- 万が一の保障:契約者が死亡・高度障害になった場合、保険料免除&満額支給
学資保険のメリットとデメリット
保険会社が倒産したらどうなる?
保険会社が万が一倒産した場合でも、すぐに契約が無効になったり、学資金が失われるわけではありません。日本では「生命保険契約者保護機構」という制度があり、保険会社の破綻時にはこの機構が契約を引き継いだり、他の保険会社が契約を承継したりする形で対応されます。
ただし、以下のような注意点があります:
- 保障内容や返戻率が削減される可能性がある
- 一部の契約は保護対象外(外貨建てなど)になることがある
- 保護の対象上限は責任準備金等の90%まで(条件により変動)
つまり、「全額が確実に守られる」とは限らず、多少の減額リスクはあるということになります。
メリット
- 計画的に教育資金を準備できる:強制的な積立により、途中で使ってしまう心配がない。
- 万が一のときの備えになる:契約者の死亡・高度障害時も学資金は満額支給される。
- 返戻率が高めのプランもある:今回のように120%超の返戻率が設定されている場合もあり、預金より有利。
- 資金の受け取り時期が計画的:大学入学時など、必要な時期に合わせて分割で受け取れる設計。
デメリット
- 途中解約で元本割れのリスクあり:学資保険は満期まで続ける前提の商品。
- 運用益は限定的:長期で考えても、投資信託などと比べるとリターンは控えめ。
- 流動性が低い:原則として途中で現金化できないため、急な資金ニーズに対応しにくい。
返戻率121.5%は高水準
1,645,480円の保険料を払って、最終的に受け取れるのは200万円。
計算上の返戻率は**121.5%**となっており、近年の低金利環境では比較的高めです。
銀行の定期預金などでは到底届かない数字なので、「確実に貯める手段」としては選択肢に入るレベルと言えます。
投資と比較したらどうなる?
たとえば、同じ金額を10年間、年利4%で投資信託(オルカンなど)に積み立て、さらに8年間運用を続けたとすると:
- 積立金額:164,548円 × 10年 = 約164万円
- 運用益込みで最終額:約278万円(年利4%想定)
この場合、学資保険の200万円に対して約78万円の差が出る可能性があります。
ただし、投資には元本割れリスクがある一方で、学資保険は満期まで継続すれば元本割れの可能性は低く、一定額が確実に受け取れる安心感があります。
特徴的だったポイント
- 10年で払い終えられる:中学進学前に支払い終了し、家計への圧迫が少ない
- 18歳から毎年40万円ずつ受け取れる:大学進学〜卒業までの費用にちょうど合う設計
- 万一の備えにもなる:契約者に万が一があった場合でも学資金は満額受け取れる
結論:確実に準備したい人には十分アリ
資産を大きく増やしたいなら投資の方が有利です。
しかし、「必要な時に、必要な額を、確実に受け取る」という点を重視するなら、今回のような学資保険は十分に選択肢になります。
教育資金の準備は、家庭の考え方やリスク許容度によって最適解が変わります。
投資と保険、それぞれの特性を理解したうえで、使い分けるのが賢い選び方といえそうです。
マネ太は投資をもう始めているので学資保険には入らずに資産形成で教育資金を作ろうと思います。






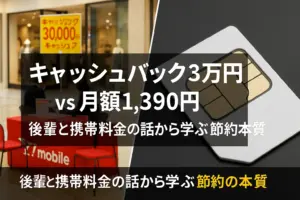

コメント